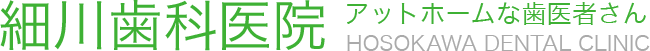お悩み内容
痛い

歯医者さんを受診するきっかけの多くが「痛み」です。
痛みの原因はさまざまで、代表的なものには以下のようなものがあります。
-
むし歯が神経近くまで進行している場合
-
根の先に膿がたまっている場合
-
歯周病によって歯肉が腫れている場合
-
親知らずが原因で歯肉が腫れている場合
それぞれの治療法として、以下のような対応を行います。
むし歯の場合
-
神経に達していなければ詰め物や金属製のかぶせ物で治療します。
-
神経まで進行している場合は神経を取り除き、根の治療を行います。
根の先に膿がある場合
-
膿がたまって痛みがある時は、膿の出口を作って内圧を下げることが必要です。かぶせ物を取り除いて根の治療を行うのが一般的です。
-
状況により、痛みが一時的と判断した場合には、金属を外さずに、かみ合わせ調整や投薬で経過をみることもあります。
歯周病による歯肉の腫れの場合
-
内圧を下げるために歯肉を切開して膿を出す処置が第一選択ですが、状況に応じてかみ合わせ調整や投薬で様子を見ることもあります。
親知らずによる痛みの場合
-
消毒や抗生物質による投薬をまず行います。(親知らずに関しては別項をご参照ください。)
以上が痛みの原因の大半ですが、例外もあります。
心と体は深くつながっており、精神的な悩みが舌や顎、場合によっては歯に痛みを引き起こすことがあります。この場合、私たちは患者さんのお話を直接伺うことはありませんが、心と体の関係についてご説明し、悩みへの意識を別の方向に向けるお手伝いをいたします。
また、痛みの原因となる歯(患歯)が特定できない場合もあります。医学は進歩しましたが、まだ人体や病気のすべてを解明しているわけではありません。そのため、痛みの程度によっては「待機的診断」として、原因が明確になるまであえて処置を控えることもあります。
私は「推測による治療」は行うべきでないと考えています。ただ、このようなケースは頻繁ではなく、通常はこれまでの知識や経験、診察・打診・X線検査・温熱診断などを駆使して痛みの原因を特定し、早急に痛みを取り除くよう努力しております。
お痛みでお困りの場合は、ぜひご連絡ください。

詰め物が取れた

取れた詰め物は、その種類によって治療方法が異なります。具体的には、「白い詰め物」「小さな金属」「大きな金属」「ブリッジ」など、どのような詰め物が取れたかによって処置が決まります。
詰め物が取れる主な原因
-
詰め物の維持力が弱まった
-
古いセメントの劣化による接着力の低下
-
歯の破折
-
むし歯の再発
-
噛み合わせによる過剰な負担
詰め物の種類ごとの対応
白い詰め物の場合
-
多くはその場で対応できます。
-
症状がなく、見た目にも問題がなければ、状況によりそのまま経過をみることもあります。
金属の詰め物の場合
-
問題がなければ再接着します。
-
むし歯や歯の欠けが原因の場合は、新しく作り直す必要があります。
-
金属の作成には歯科技工士の作業が必要であり、複数回の通院が必要です。ブリッジの場合はさらに治療期間が長くなります。
神経の有無による治療の違い
取れた歯の神経があるかないかで治療内容が変わります。
-
神経がない場合、X線検査で根の先に膿が溜まっていることがあります。その場合、根の治療が必要になることもあります。
-
ただし、根の先に膿があるからといって必ず治療が必要とは限りません。根の治療は成功率が必ずしも高くなく、治療しても再発する可能性があります。そのため治療の判断は慎重に行っています。
実際に長期的にみると、根の先の膿は大きくなったり小さくなったりすることがあり、これは患者さまの免疫力や体調が影響しています。また無症状の場合も多く、何度も根の治療を繰り返すことは歯根破折という抜歯の原因に近づくリスクがあります。
私の踏み込むべき基準としては、
-
明らかな大きな病変がある場合
-
排膿や噛んだ時の痛みがある場合
-
無症状でも根の薬が消失している場合
には根の治療を行うことが望ましいと考えています。
詰め物を放置した場合のリスク
詰め物が取れたまま放置すると、
-
歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなり、歯周病が進行する
-
歯が動いて噛み合わせが変化する
といった問題が起こる可能性があります。
そのため、詰め物が取れた場合は、なるべく早めに治療を受けることが大切です。ご不安な場合はお気軽にご連絡ください。

はぐきがら血が出る

歯ぐきからの出血は主に歯肉炎または歯周炎が疑われます。
-
骨が破壊されていない場合を「歯肉炎」
-
骨が破壊されている場合を「歯周炎」
と呼びます。
これらは抵抗力(免疫力)に関連しており、一般的には20代以下では歯肉炎が、30代以降では歯周炎が多く見られます。どちらも自覚症状が少ないため、気づいた時には骨の破壊がかなり進行しているケースも珍しくありません。
主な症状
-
歯ぐきからの出血
-
口臭
-
歯がしみる
-
歯がぐらつく
-
噛みにくくなる
特に「歯ぐきからの出血」は、これらの症状の代表的なものです。
出血の主な原因と対策
毎日の歯磨きをしていても、歯ブラシが歯ぐきに適切に当たらず、プラーク(歯垢)が残ってしまうことが原因です。このプラークをきちんと取り除くことで、出血は次第に改善します。
適切な回数・時間の歯磨きと、正しいブラッシング方法を行うことが大切です。
歯周病の治療とブラッシング
歯周病は治らない病気と思われがちですが、適切なブラッシングを継続することで、時間はかかりますが確実に改善します。逆に言えば、ブラッシングを行わない限り歯肉炎・歯周炎は治りません。
歯ブラシというと「汚れ落とし」のイメージが強いですが、実際は長期間の丁寧なブラッシングによって治療的な意味合いも生まれてきます。これは長期的な症例研究でも証明されています。歯石除去や外科的な治療だけではなく、適切なブラッシングが治癒への最重要ポイントです。
歯周病治療で重要なポイント
しかし、歯周病の原因は複雑で、単純に歯ブラシだけでは解決しません。現在の歯周病治療では以下が重要とされています。
-
「炎症」と「力(噛み合わせなど)」のコントロール
-
生活習慣の改善
-
精神的なストレスや心の状態の影響
つまり、歯周病の治療は生活習慣全体や心理面を含めた総合的なアプローチが必要となるため、非常に治療が難しい病気です。
生活習慣を変えることは一時的には簡単でも、それを長期間継続するには強い精神力が必要です。歯周病を根本的に治療するということは、自分自身の生活習慣や心理的な側面まで見直すことになります。
細川歯科医院が「生活習慣の改善」を重要視しているのは、このような理由からです。また私自身が臨床心理学を学んでいるのも、歯の健康を守る上で「心の問題」を無視できないと感じているためです。
歯周病は自覚症状が少なく、知らないうちに進行する病気です。歯ぐきの出血が気になる方は、ぜひご相談ください。現在のお口の状態を詳しく把握し、ブラッシング指導だけで対応可能なのか、治療が必要なのか、それ以上の介入が必要なのかを判断し、患者さまに適切なアドバイスをさせていただきます。

親知らず

親知らずの痛みを訴えて来院される方は多くいらっしゃいます。特に台風など気圧の変化がある日は、複数の方が同時に痛みを感じることも珍しくありません。
多くの患者さまは「痛い=すぐ抜歯=痛みが取れる」と考えがちですが、実は急性症状(強い痛みや腫れ)がある場合、細川歯科医院では通常すぐに抜歯を行いません。その主な理由は、以下の通りです。
急性症状時に抜歯しない理由
-
痛みや腫れがある時は麻酔が効きにくくなります。炎症や膿の影響で麻酔薬の効果が妨げられ、十分な麻酔が得られないことがあります。
-
強引に抜歯を行ったとしても、麻酔が切れた後の痛みが非常に強くなり、患者さまの負担が増します。
そのため、「痛み」や「腫れ」のない落ち着いた時期に抜歯を行うほうが、患者さまにとっても歯科医院にとっても良いのです。
痛みや腫れへの対応
まずお口の状況を確認し、症状に応じて以下のような処置を行います。
-
親知らずが上下で噛み合い、歯肉を傷つけている場合は、出ている歯を削って歯肉の回復を促します。
-
歯肉が化膿・炎症を起こしている場合は、消毒と投薬を行い症状を落ち着かせます。
投薬などで症状が落ち着いた後に、抜歯を希望される方もいますし、「症状が治まったので抜歯をもう少し様子を見たい」という方もいらっしゃいます。
統計を取ったわけではありませんが、細川歯科医院では痛みが落ち着くと抜歯を先延ばしにされる方が多いようです。ただし、一度腫れた親知らずは再び腫れる可能性が高いため、その旨は患者さまに必ずお伝えしています。
抜歯を迷ったときの基準
抜歯を迷っている方への一つの判断基準として、「患者さま自身の心構え」を大切にしています。気持ちが整わない場合は、無理をせず気持ちが整うまで時間を置くことをおすすめします。
また、類似の選択(「削るか削らないか」「自費か保険か」など)についての私の考えは以下の通りです。
-
「削るか削らないか」で迷ったら削らない方を選択
-
「自費か保険か」で迷ったら保険をおすすめ
ただし、患者さまが抜歯を決意されても、親知らずの状態によっては細川歯科医院で対応できないこともあります。その場合は大学病院をご紹介します。
まずはお口の状態を確認し、痛みや腫れを和らげた上で、患者さまと一緒に今後の方針を決定していきますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

定期検診(歯石除去)

定期的な歯科検診の大切さ
歯や口の健康を保つためには、歯科での定期検診が非常に重要です。毎日丁寧に歯磨きをしていても、生活習慣や歯の性質によって、むし歯や歯周病になりやすい方もいます。
定期検診を受けることで、むし歯や歯周病などの問題を早期に発見できます。そのため、症状が進行する前に適切な治療が可能です。
一方で、検診を受けずに問題を放置すると、痛みや腫れなどの症状が現れたときには、すでに悪化しているケースが多くなります。定期検診を習慣化して、歯と口の健康を守りましょう。
歯周病の危険性について
歯周病は「沈黙の病気」とも呼ばれ、日本人の80%以上がかかっていると言われています。ほとんど痛みを感じないため、自覚した時にはすでに歯がグラグラして重症化していることが少なくありません。
さらに歯周病は一本の歯にとどまらず周囲の歯にも広がり、動脈硬化や骨粗鬆症、脳梗塞など深刻な病気を引き起こすリスクも高まります。
定期検診のメリット
定期検診の最大のメリットは、歯科医師や歯科衛生士が歯や歯茎の小さな変化を早期に発見できることです。痛みや腫れなどの症状が出たときには、すでにむし歯や歯周病が進行してしまい、最悪の場合は抜歯が必要になることもあります。
しかし、定期的にチェックを受ければ、こうしたリスクを大幅に軽減できます。また、問題が見つかっても歯を削らずに済んだり、簡単な処置で炎症を抑えることが可能です。
また、かぶせ物や詰め物をしている場合、その隙間に溜まった汚れを歯ブラシだけで完全に取り除くことは難しくなります。そのため、内部でむし歯が進行してしまうケースも少なくありません。定期検診では、視診だけでなくレントゲン撮影も行い、過去の画像と比較しながら歯の状態を正確に把握し、適切な処置を行います。
さらに、定期検診は治療後の歯の経過確認にも役立ちます。一度治療した歯は、時間が経つにつれて再確認されることが少なくなりがちですが、定期的に検診を受けることでその維持管理が可能になります。万が一、治療後に問題が起きても、症状が悪化する前に迅速に対応できます。
病気予防と医療費削減
国も病気の予防を目的として、定期的な歯科検診やメンテナンスを推奨しています。例えば、むし歯や歯周病を放置すると、細菌が血流に入り込み、糖尿病や心臓疾患、脳梗塞などを引き起こす可能性があります。
健康なうちから定期検診を受けることで、これらの深刻な病気のリスクを減らすことができます。また、それが結果として生涯にかかる医療費を削減することにもつながります。
定期検診の頻度について
細川歯科医院では、歯の定期検診を基本的に4ヶ月に1回のペースで行っています。
ただし、お口の状態によって検診の頻度は変わります:
-
むし歯や歯周病のリスクが高い方:1〜2ヶ月に1回
-
お口の状態が良好な方:6ヶ月に1回
また、年齢を重ねるにつれて歯周病のリスクは高くなるため、ご高齢の方は若い方よりもこまめな検診をおすすめしています。
磨き残しによるプラークは、時間が経つと歯石になり、放置すると除去が難しくなるだけでなく、大きな病気の原因にもなります。
そのため、最低でも3〜6ヶ月に1回は定期検診を受けることが大切です。
定期検診で健康な歯を守りましょう。
※費用に関してですが、初診時においては踏み込んだ治療がなければX線代を含めて大体2500円前後です。定期検診(クリーニング)は2回目以降に行い、その際の費用は2500円~3000円前後となっております。
むし歯

むし歯を繰り返さないためには、「なぜむし歯になったのか」をご自身で考えることが何よりも大切です。その原因を見つけなければ、どれだけ治療をしても再発を防ぐことはできません。
実際のところ、歯科治療の多くは「やり直し」の治療です。特にむし歯は、原因を十分に考えず、安易に削って詰める治療を繰り返した結果、再発を引き起こしていることが多いのです。その意味では、原因を追究せずに安易な治療を行ってしまう私たち歯科医療者にも責任があります。
「むし歯はすべて治療すべき」と思われがちですが、実は治療しない方がよい場合もあります。原因を考えずにむし歯を削ると、かえって隣接した部分に新しいむし歯を作りやすくし、結果的に歯を失うリスクを高めてしまうからです。
細川歯科医院では、以下のような項目を総合的に判断し、治療が必要か、経過観察でよいかを決定しています。
-
年齢や問診内容
-
お口の状況やX線写真
-
唾液の性質
-
むし歯が進行しているかどうか(活動性・非活動性)
-
歯間清掃用具の使用状況
-
患者さまご自身のケアへの協力度
上記の一つひとつが「むし歯を削るか削らないか」を決める重要な要素です。総合的に評価し、慎重に判断しています。
実際には、「黒い点が気になる」と来院される患者さまの多くが、むし歯ではなく着色の場合が多いのです。私は唾液の持つ自然治癒力を尊重し、安易に削らないことを心がけています。また、むし歯は急速に進行しない場合も多く、経過観察で十分なことも多々あります。
私自身が予防歯科の勉強会で学んだ最も重要なことは、「安易に削らず、削るべきかどうかを慎重に悩むこと」でした。実際のところ、歯科医によってむし歯を削る基準は異なります。ある先生は削らないと診断し、別の先生は削ると判断することもあります。
患者さまとしては、「むし歯です」と言われ削った方が安心感があるかもしれません。また、かかりつけ医に「むし歯はない」と言われても、他の歯科医院で「むし歯があります」と指摘されると、そちらを信じやすいかもしれません。しかし、安易に削ることは、後々のむし歯リスクを高めることになります。
このような理由から、むし歯の状態によっては削らずに経過観察をおすすめすることがあります。ただ、それを十分にご理解いただくには時間と労力が必要であり、診療時の短時間では伝えきれないことも多いのです。
細川歯科医院では、お話だけで終わることもありますが、それは患者さまの歯を守るための選択の一つです。気になることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

しみる

「歯がしみる」という症状を訴える患者さんは、最近特に若い方に増えています。多くの方が「むし歯」を疑って来院されますが、実際には必ずしもそうとは限りません。
実はこの「しみる」症状は、一般的にテレビCMなどでも知られている「知覚過敏」である場合が多く見受けられます。
歯がしみる主な原因
歯がしみる原因として代表的なのは、「食いしばり」や「歯ぎしり」など、歯に強い力が加わることです。特に就寝時の歯ぎしりや、無意識に歯を噛み合わせる「歯列接触癖」がある場合、歯への負担が増えて症状を引き起こします。
歯は本来、食事以外の時間は接触しない状態が正常です。歯が長時間接触したり、強い力で噛み合わせたりすると、歯や骨にダメージが及び、「しみる」症状につながります。
「力」による症状への対応
力によって引き起こされる歯のしみへの対応としては、次のような処置があります。
-
しみる歯の高さを調整する「咬合調整」
-
就寝時に歯を守るためのマウスピース(ナイトガード)の装着
これらの処置を行うことで、時間はかかりますが症状は確実に軽減します。
ストレスとの関連
中には、力への対応をしてもなかなか症状が改善しないケースがあります。この場合、本人が気づかないうちにストレスを抱え込んでいる可能性があります。
ストレスの影響を強く受けている場合は、ご自身に合ったストレス解消法を見つけることで、心にゆとりが生まれ、自然と症状が改善していくことがあります。
一時的な処置のリスク
「しみる→薬を塗る→一時的に改善→再発」を繰り返すだけでは根本的な解決になりません。また、繰り返しの処置によって唾液の働きが妨げられ、むし歯のリスクが高まる場合もあります。
しみる症状が軽度であれば、特別な処置をせず、その症状と上手に付き合うことも選択肢の一つです。
その他の原因
これまで主に「力」による知覚過敏について説明しましたが、当然ながら「むし歯」や「歯周病」も「しみる」原因として挙げられます。
もし歯のしみる症状でお悩みの方は、その原因を詳しく探り、一緒に最適な対策を考えてまいりますので、お気軽にご連絡ください。

入れ歯が合わない

入れ歯の適合性は、「部分入れ歯」か「総入れ歯」か、またお口の中に残っている歯や骨の状態によって大きく異なります。
部分入れ歯の適合性について
部分入れ歯は、残っている歯にバネをかけて安定させるため、その歯の状態が非常に重要です。歯の状態が悪いと入れ歯の安定性が低下します。そのため、安定した入れ歯を作るには、まず残っている歯の治療が必要です。状態が悪い場合は、隣接する歯と連結したり、無理に歯を残さずに抜歯をしたり、歯を削って磁石を使って安定性を高めたりすることもあります。
削ったり抜いたりすることはなるべく避けたいですが、入れ歯の安定性や全体の噛み合わせのバランスを考えると、これらの処置が必要になることもあります。
総入れ歯の適合性について
総入れ歯の場合、安定性は骨の量に大きく左右されます。骨が少ないとどうしても不安定になります。また、骨の量は年齢とともに減少するため、理想的な入れ歯を作ることが難しくなる場合もあります。
「他院で何度も総入れ歯を作ったが合わない」という方が多くいらっしゃいますが、そのような場合、残念ながら現在お使いの入れ歯以上のものを作ることが難しいケースもあります。この場合は、状況を受け入れ、現状に最も適した方法を探していくことが重要です。
保険適用と自費治療について
入れ歯を作製する際には、保険適用か保険外(自費)かによっても違いがあります。自費での治療の場合、時間をかけて古い入れ歯から患者さまに合った最適な噛み合わせを探り、何度も調整を繰り返しながら、よりフィットする入れ歯を作ることが可能です。
一方、保険適用の範囲では調整のための時間に制限があるため、患者さま一人ひとりに最適な噛み合わせを細かく調整することが難しくなり、新しく作った入れ歯より古い入れ歯のほうが合っていると感じる場合もあります。
細川歯科医院の取り組み
細川歯科医院では、噛み合わせのトータルな治療を最も得意としています。数多くの講演会や勉強会に参加し、さまざまな臨床経験を通じて得た知識を活かし、「しっかり噛める」と多くの患者さまに喜んでいただいています。
入れ歯の問題を感じている方は、お口の状態や現在使用中の入れ歯を拝見したうえで、新たに作成すべきか、現在のままで様子を見るかなど、最適なアドバイスをいたします。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。